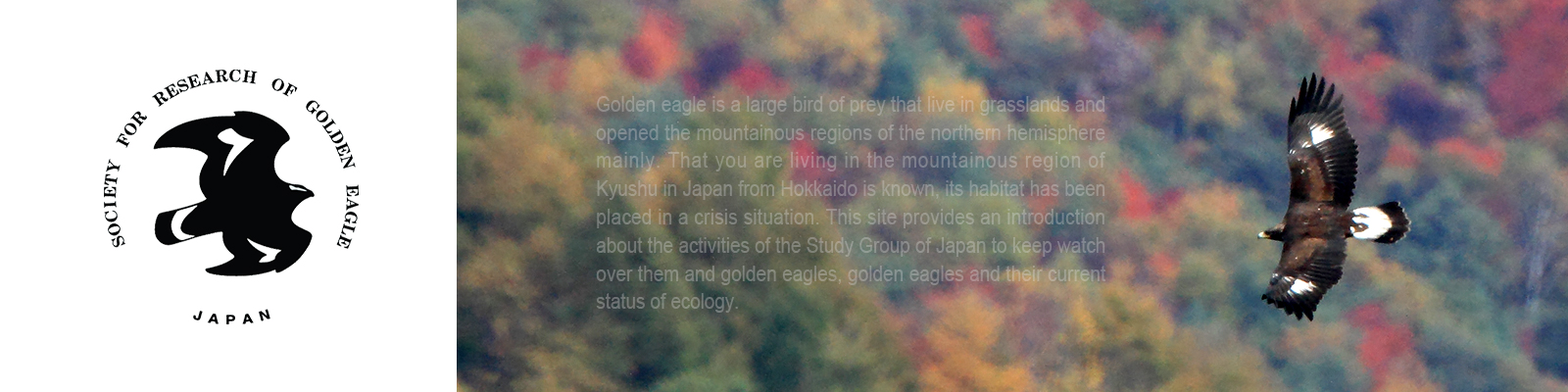生息・繁殖状況調査報告2022の更新
生息・繁殖状況調査報告を最新の集計結果(1981年~2022年/地区別は1996年〜2022年)に基づいて更新しました。 (クリックすると詳細ページに移動します) イヌワシについて > つがい数の減少と繁殖成功率低下 続きを読む →
「大船渡第一・第二太陽光発電所事業 環境影響評価準備書」に対する意見
日本イヌワシ研究会は、自然電力株式会社に対し、イヌワシに象徴される貴重な自然環境を蔑ろにする「大船渡第一・第二太陽光発電所事業計画」の白紙撤回を求めます。 提出日 2025年3月31日 提出先 自然電力株式会社 代表取締 続きを読む →
生息・繁殖状況調査報告2021の更新
生息・繁殖状況調査報告を最新の集計結果(1981年~2021年/地区別は1996年〜2021年)に基づいて更新しました。 (クリックすると詳細ページに移動します) イヌワシについて > つがい数の減少と繁殖成功率低下 続きを読む →
Aquila chrysaetos No.28 / 2022年度発行
特集 全国イヌワシ生息数・繁殖成功率調査報告(1981-2015) 報告 1. 紀伊山地におけるイヌワシの生息繁殖状況~ペアコードNo.8003の発見から現在まで~ 【紀伊山地イヌワシ調査グループ】 合同調査報告 イヌワ 続きを読む →
Aquila chrysaetos No.27 / 2020年度発行
特集 長野県北部における1970年代後半と近年のイヌワシの繁殖状況と生息環境の変化【片山磯雄】 報告 2014・2015年イヌワシ合同調査(糸魚川周辺地域)のその後【小澤俊樹】 短報 二ホンイヌワシの野生個体における寿命 続きを読む →
「(仮称)上沼風力発電事業 計画段階環境配慮書」に対する意見
株式会社グリーンパワーインベストメントによって進められている表記事業について、当会は同社の代表取締役社長 坂本満 様に意見書を提出しました。 提出日 2024年8月9日 提出先 株式会社グリーンパワーインベストメント 代 続きを読む →
「(仮称)栗子山風力発電事業」についての回答書を受領
2024年2月29日に提出した要望書に対して山形県知事から回答をいただきました。 回答日 2024年4月5日 回答元 山形県知事 吉村美栄子様 ご覧の環境ではPDF表示がサポートされていません。PDFファイルをダウンロー 続きを読む →
「(仮称)栗子山風力発電事業」についての要望書を提出
JR東日本エネルギー開発株式会社によって進められている標記事業について、当会は山形県知事に要望書を提出します。 提出日 2024年2月29日 提出先 山形県知事 吉村美栄子様 ご覧の環境ではPDF表示がサポートされていま 続きを読む →
プレスリリースのお知らせ(山形県知事に要望書を提出)
JR東日本エネルギー開発株式会社による「(仮称)栗子山風力発電事業計画」は絶滅危惧種イヌワシの生息を脅かす恐れがあるため、事業の中止を求める要望書を山形県知事に提出します。 提出日 2024年2月29日 提出先 山形県知 続きを読む →
「(仮称)栗子山風力発電事業 環境影響評価準備書」に対する意見
JR東日本エネルギー開発株式会社によって進められている表記事業について、当会は同社の代表取締役社長 松本義弘 様に意見書を提出しました。 提出日 2023年10月16日 提出先 JR東日本エネルギー開発株式会社 代表取締 続きを読む →